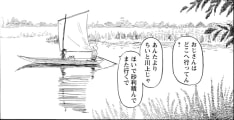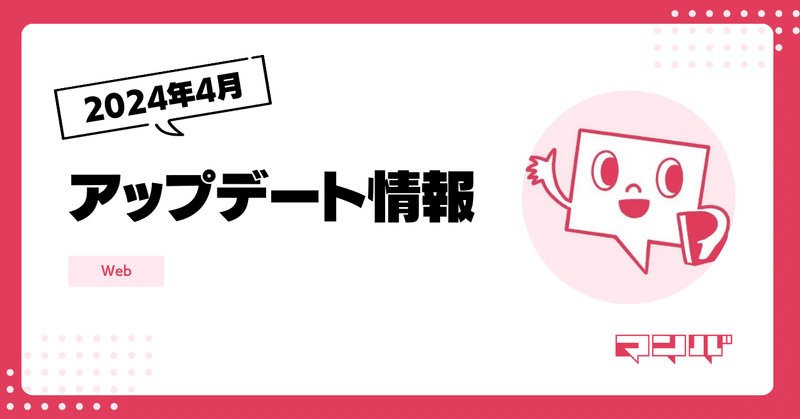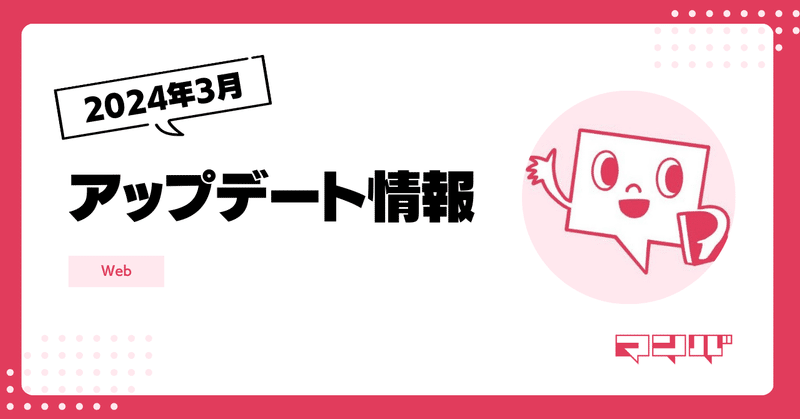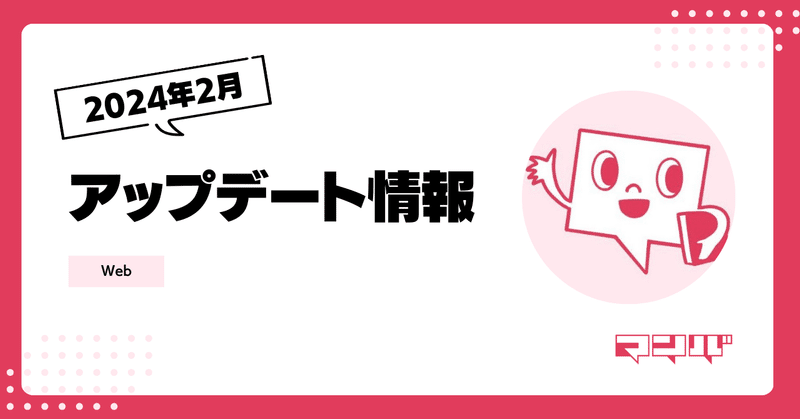2016年11月、ついにアニメーション版『この世界の片隅に』が公開された。アニメーション好きばかりでなく、原作であるマンガのファンからも高い評価を受けている。2回あるいは3回観たという知人もいる。わたしは4回観た。名作であることは間違いない。しかし、名作名作と言っているだけでは飽き足らない。そろそろこの物語について、ネタバレも含めて自由に語りたくなってきた。
わたしはふだん、誰か一人の行為ではなく、行為と行為のやりとり、すなわち相互行為を扱う仕事をしている。だから、アニメーションで交わされる会話をきくときには、特定の誰かの声の魅力に聞き入るよりも、誰かと誰かの相互行為において彼らの声がどんな風にきこえてくるか、それを手がかりにアニメーションの受け手はその場面をどんな風に理解しているかが気にかかる。また、原作とアニメーションのどちらがよいか、ではなく、アニメーションが原作をどう翻案することによって、原作から何を汲み取っているか、そのことが観客に何をもたらしているかに興味がある。
そこでこの連載の場を借りて、しばらくのあいだ「この世界の片隅に」の原作マンガとアニメーション版を往復しながら、これらの作品で起こっていることを少しずつ掘り起こしていこうと思う。
まず最初に扱うのは、この物語に登場する二人の姉妹、すずとすみのことである。
原作マンガの「この世界の片隅に」で印象的なやりとりがある。食卓で主人公の浦野すず達が祖母と食事をしているときのこと。「箸を遠う持つ子は遠くへお嫁に行く言うけえね」という祖母は箸を遠く持っているが、実は草津のすぐ隣の古江から嫁いできた。それを見て、すずの妹のすみが皮肉る。「古江から草津でそんとなじゃ 満州やなんかへ嫁(い)っての人は火箸でも足らんね」。すかさず、すずが見とがめて「と言いながらも箸を持ち直す浦野すみであった」とからかう。

このすずのセリフには、わたしたちが自分たちのことを物語化するときの感覚が、うまく表れている。まず、方言から標準語に切り替えることで、ことばはいま話している当事者の近しさを離れて、まるで第三者が物語を語るように響く。さらに、妹を愛称ではなくあえて「浦野すみ」とフルネームで呼ぶことで、物語の中に取り込む。「と言いながらも箸を持ち直す浦野すみであった」というすずのことばは、あたかも活動弁士のように、あるいはドラマのナレーションのように、すみを、そして自分たちの居るこの場所を物語にしてしまう。
こうした物語化による遊びは、姉妹の会話の端々に表れる。たとえば原作第6回の、すみとすずのやりとり。女子挺身隊に通うすみは、美男子の将校さんから時々こっそり食堂の食券をもらっていることを姉にもらす。すずは少しおおげさにこういう。「思いがけず陸軍の機密を知ってしもうた」。一方すみは、すずの頭に(おそらく嫁入り先での悩みごとによる)ハゲができていることに気づいて「うち思いがけず海軍の機密に触れてしもうたみたい」と小さく逆襲する。ちなみに、「将校さん」の親切話は、すみの語りの定番なのだが、アニメーションでは、すみ役の潘めぐみがそのはしゃいだ口調を、すず役ののんとは対照的な明るい声で好演している。
アニメーション版「この世界の片隅に」のエピソードのほとんどは原作からとられているのだが、その一方で、交わされている会話には、見逃すことのできない変更がいくつか加わっている。その一つが、冒頭、すずと周作が出会った「人さらい」のバケモノのエピソードだ。原作ではこのエピソードは独立したお話として描かれており、すず、周作とバケモノとはこんな風に直接会話を交わす。
バケモノ「夜がくる前に山へ帰らんとえらいことになるわい」
すず「えらいこと? どんな?」
バケモノ「…… …… …… うるさい いらん事きくなあ」
ところが、アニメーション版では、このエピソードはすずの描く絵物語であり、片渕監督は、すずの描いている横にすみを配し、姉すずが妹すみに語っている場面として翻案しているのである。そこでは、バケモノの声は、まるですずからすみに宛てられたかのように引き取られる。
バケモノ「夜が来る前に帰らんとえらいことになる」
すみ「どうえらいことになるんじゃろ?」
すず「まあ見とりんさい」
のんが発するこの「まあ見とりんさい」のイントネーションはいかにも自然で驚かされるが、それ以上に、微かに笑いを含ませながら聞く者を物語の先へと巻き込んでいく彼女の声のニュアンスがすばらしい。こうした語り口調は、もしかしたら、かつて朝の連続テレビ小説『あまちゃん』で、主人公とともにナレーションをも勤めた経験から得られたものかもしれないが、それが広島弁という全く異なる方言でも個性を減じることなく自然に響いているのは、明らかに彼女の才能のおかげだろう。たいそう耳のいい女優さんだと思う。
さて、この姉妹のやりとりでもう一つ注目したいのは、すみの方である。幼い周作がすずのモモヒキのスソに記されていた名前を目ざとく見つけて「あんがとな浦野すず」と初対面のすずの名前をフルネームでよんだのを、すみは大ウケして繰り返す。
すみ「きゃはははは『あんがとなうらのすず』きゃははは」
原作にはないこの小さな台詞の付加は、思いがけない効果をもたらす。姉をフルネームで呼ぶことで物語と戯れるすみのこの台詞をきいてから、さきほどの箸のエピソードに観るとき、「と言いながらも箸を持ち直す浦野すみであった」というすずの台詞は、まるで「あんがとなうらのすず」というすみの笑いへの、かわいらしい逆襲のように響くのである。自他の行為を芝居めかして語り、お互いを物語の中に引き入れる姉妹の愉しみ。アニメーションは、冒頭のエピソードを姉妹の会話に翻案することによって、この愉しみを、原作から掬い上げているのだ。
呉に嫁いだすずが失ったのが、この妹との活き活きとした広島弁のやりとりである。それは、呉弁の飛び交う北條家ですずの口数が少ないことからもわかる。とりわけ径子の多弁は、すずの遠慮がちなことばとは対照的で、それはむろん小姑と嫁という立場の違いを浮き彫りにするだけでなく、呉と広島、二つの土地の言語圏の違いを露わにする。径子役の尾身美詞のいかにも険のある口調によって、観客は、たとえ呉弁と広島弁の違いに明るくなくとも、すずをひるませる径子の声が呉の家や土地に深く依っているのだということ、呉と広島の間に明らかな言語の違いがあることを悟る。
そして、呉と広島の対比は、映画の後半、昭和20年7月にすずを見舞いにきたすみとすずとのやりとりによって、さらにくっきりと浮かび上がる。「ハイ!古着じゃが純綿よ」「スフ入っとらんの?」「うん、破れんで!」「うわぁーっ!」。久し振りに広島弁を活き活きと話すすずとすみのこの会話は、マンガでも交わされているのだが、アニメーションの声を伴うと、その場違いさ加減がいたいほど伝わってくる。呉という場所において二人の会話が呉弁ではなくよそ者ことばである広島弁でなされていること、そしてそのよそ者の声が呉の家であまりに高く響き過ぎていることは、径子ががらりと戸を開けて茶を差し出すのを待つまでもなく明らかなのである。

そして、すみとすずの会話が、呉の家だけではなく、呉の街に似つかわしくないこともまた、外に出て明らかになる。北條家を出て、すみはお得意の話、将校さんとの浮ついたやりとりの話を語るうちに、ふと声を潜める。彼女の広島弁は、焼け野原を前にして不似合いなほど明るく響いている。すみは急に、道ばたの線香の前にしゃがみ込む。そして観客は気づく。昭和20年7月のこの時点では、広島ではなく、軍港都市である呉こそが集中爆撃を受けていたこと。むしろ呉は広島から救援や同情を寄せられる場所であったことを。だからこそ広島から来たすみは躊躇なく道ばたの線香の前にしゃがむことができ、逆に当事者であるすずはそれを呆然と立って見るしかなかったのである。
すみの広島弁を響かせてしまう、呉の、どうしようもない焼け野原の広さ。この、呉の無惨な姿と平穏な広島の対比を、アニメーションの声は浮き彫りにする。アニメーションでは7月の呉空襲の翌朝、「広島より握り飯が届いておりまーす!!」という巡査の声を呉の街に響かせているのだが、それもまたこの二つの都市の対比に関わっている。
呉と広島のこのような違いは、昭和20年を単に「終戦の年」「原爆の年」とまとめることではけして見えてこない。呉での一日一日の生活を順に追い、昭和20年7月にたどりつくことで初めて浮かび上がってくるものだ。
半年後の昭和21年1月、広島ですみは蒲団に伏せっている。呉からすずが久し振りに訪れると、「ちいと目まいがするだけ」と言ってから少しおどけた調子でこう付け加える。「ああ無念じゃ姉上……この寒空の下、海苔の仕事が手伝えんとは…」。相手を「姉上」と呼び芝居めかしたすみのセリフには、お互いに物語ることを愉しみとしてきた者どうしならではのおどけた口調がこめられている。つい半年前のすずとすみの立場は、まるで変わってしまった。まるで「あんがとうらのすず」と「箸を持ち替える浦野すみ」が入れ替わるように。
いつもは明るく振る舞っているすみの左手には不吉なしみができている。「すずちゃん うち治るかねえ?」。「夕凪の街 桜の国」の作者は、すみのその後について書いてはいない。その代わりに、すずは、すみの左手をとって「治るよ 治らんとおかしいよ」と言う。二人は左手を天井に掲げる。その所作は、見えない物語を召喚するかのようだ。
この姉妹のやりとりの最中に、片渕監督は、原作にはない会話を織り込んでいる。それは、すずの描く鉛筆マンガ「鬼イチヤン冒険記」をめぐるものだ。原作では無言で描かれるこのマンガを、アニメーションはまたしても姉妹の会話の生みだす物語として翻案している。それはこんなやりとりだ。
すずは、まるで天井に右手をぶらりと持ち上げて「あー、手がありゃ鬼いちゃんの南洋冒険記でも描いてあげられるのにねえ」と言う。天井をノートに見立てるかのように手を掲げ、その木目をなぞるのは、すずが幼い頃から繰り返してきた所作であり、すずはその力で、座敷童子を我知らず呼び出したことさえあった。すみが、まるで子供に戻ったようにすずにお話をねだる。
「それどんなん?ねえ、どんな話?」
「うーん…鬼いちゃん輸送船が難破して、南の島に椰子の葉で家作って」
「うんうん」
すみが楽しげにあいづちを打つと、あたかも姉妹の会話に力を得たかのように、鉛筆画の鬼いちゃんが空想の中でみるみる描かれていく。鬼いちゃんは南国でたくましく生き抜き、髪とひげをボウボウに生やし、籠を背負ったバケモノのような姿となって南国を旅立つ。
バケモノはやがて、広島の橋の上で佇んでいるすずと周作のそばを通り過ぎる。このとき、わたしは、物語の冒頭に表れたバケモノのこと、それがアニメーション版では姉妹の会話によって語られていたことを不意に思い出す。原作では、このバケモノの再登場によって、物語に一つの円環が形作られるのだが、アニメーション版では、そこに、姉妹の会話というもう一つの環が重ねられているのである。
すず、すみ、二人の姉妹が交わす親密な広島弁は、二人がおそれていた兄、戦争に赴き石ころ一つにすり替えられて帰ってきた兄に、物語の生を与えた。声と声が生んだバケモノ。それは、アニメーション版がこの三人兄妹のためにこっそり用意した、新しい生の形なのかもしれない。
『アニメーション版「この世界の片隅に」を捉え直す』の一覧
(1)姉妹は物語る
(2)『かく』時間
(3)流れる雲、流れる私
(4)空を過ぎるものたち
(5)三つの顔
(6)笹の因果
(7)紅の器
(8)虫たちの営み
(9)手紙の宛先
(10)爪
(11)こまい
(12)右手が知っていること
(13)サイレン
(14)食事の支度
(15)かまど
(16)遡行
↓↓記事の感想や『この世界の片隅に』について語りたい人はマンバへ↓↓


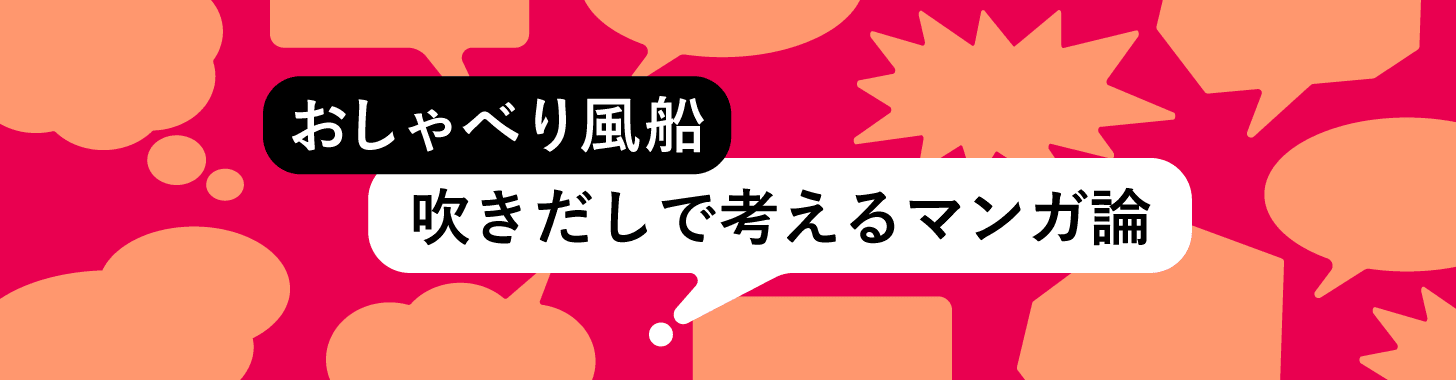







![庶民から見た戦争マンガ|テーマ別に読む[本当に面白いマンガ]第4回](https://res.cloudinary.com/hstqcxa7w/image/fetch/c_fit,f_auto,fl_lossy,h_234,q_auto,w_234/https://magazine.manba.co.jp/wp-content/uploads/2023/08/ManbaMagazineEyecatch.001-2.jpeg)